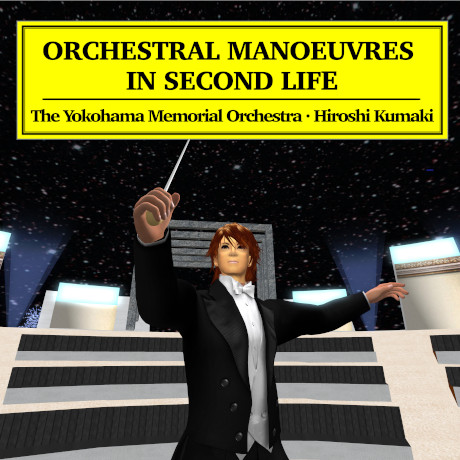前回に続いてメシアンである。
小澤征爾さんがメシアンからその作品の演奏を任されていたことは
前にも書いた通りだが、その最後の大仕事とも言えるのが、
メシアン唯一のオペラで、上演に4時間を要する大作
『アッシジの聖フランチェスコ』の初演だったと考えている。
これはパリ・オペラ座の委嘱で制作されたもので、
その初演は1983年11月28日にオペラ座で、
小澤さんがパリ・オペラ座管を指揮して行われた。
その時の録音がリリースされていて、これはとても貴重なものだ。

僕にとってこの CD が貴重なのは、この曲については、
前にも書いた武満徹さんとの対談集『音楽』の中で語られていて、
この本が出てすぐ読んだ僕にとっては、
1941年作曲の『世の終わりのための四重奏曲』とも
1949年作曲の『トゥランガリーラ交響曲』とも異なり、
リアルタイムの、現在進行形のメシアンの新作だったからだ。
その、1979年頃に行われた対談のなかにこんな会話がある。
「武満 メシアン先生は目下大作にとりかかっているんだろう?
小澤 二年後にそのオペラを指揮しなきゃいけない。それがなんと楽譜で三千ページあるんだ。この間、ピアノ・スコアを見てきたけれど。今、オーケストレーションしてるらしい。
武満 あの人のは、もう少し短くなるといいけれどね……。『キリストの変容』もちょっと長過ぎるね。あの人は、あそこまでやらないと、どうしても満足できないんだよ。おれなんかは、一生かかっても三千ページは書けっこない(笑)。
小澤 この間もメシアン先生から念を押されて、やることになっている。一九八二年に。
武満 七管編成でしょ。
小澤 七管編成で、オンドマルトノというのが三台。
武満 そんな大編成で、歌って、聞こえるのかな。
小澤 それが聞こえるんだって。ちゃんと計算できているみたいよ。すごいねェ。」
おお、おお、『トゥランガリーラ』でも使われた大好きな楽器
オンドマルトノが3台も使われるとは!
そして、七管編成なんて聞いたこともないんだけれども。
普通のオケの曲だと三管とか四管ですよ。
この何管というのは、木管楽器のフルートやクラリネットなどの
パートの本数を基準にして呼ばれるけれども、
木管の本数が決まるとそれに応じて金管の本数、弦の台数も決まり、
オケ全体でどのくらいの演奏家が必要になるかが決まるのだが、
実際、編成表を見るとフルートだけで、
・ピッコロ×3
・フルート×3
・アルトフルート×1
となっていて実際7本必要なのだ!
(普通はピッコロやアルトフルートは何人かいるフルートの1人が
持ち替えで対応するものだが。。。)
そうやって8年をかけて出来上がったのは全3幕8場から成る
上演時間4時間にも及ぶオペラで、それだけに聴き終わった時の
感動はとても言い尽くせぬものがある。
そうそう上演されることのない巨大でレアなオペラなので
ここで簡単にどんな曲か説明をしておくと、
アッシジの聖人フランチェスコ
(日本では伝統的にフランシスコと呼び慣わされている)の生涯を
8つの情景で描くもので、
オペラや楽劇に付き物の序曲や前奏曲といったものはなく、
またアリアらしいものもない。
ただ、ヴァーグナーの楽劇のように登場人物それぞれに
ライトモチーフのような主題があり、
中でもフランチェスコや天使には複数の主題が割り当てられている。
更に、メシアンと言えば鳥の研究と
その鳴き声を音楽で表現することで有名だが、
この作品でも、それぞれの登場人物に特徴的な鳥が割り当てられ、
舞台を見ていなくてもその鳥のさえずりで例えば天使が現れたことが
わかるようになっているという仕掛けである。
これは、聖フランチェスコが鳥に説教をしたという伝説から
当然そのシーンがこのオペラには組み込まれているわけだけれども、
アッシジのあるウンブリア地方によくいる鳥から始まり、
世界中から34種の鳥が選ばれ、その囀りが音で表現される。
34の鳥の中には日本のホオアカ、フクロウ、ウグイス、
そしてホトトギスも選ばれ、登場する。
それぞれの情景の内容は次の通り。
第1景『十字架』
木琴を始めとする鍵盤打楽器によるヒバリの囀りで幕を開ける。
続いて修道士レオーネが『伝道の書』の「道にはおののきがある」
を下敷きに「私は恐ろしい」と歌う。
そこにズグロムシクイ(カピネラ)の囀りに導かれ
フランチェスコが登場、「完全なる歓び」について語る
第2景『賛歌』
フランチェスコと修道士たちが「太陽の讃歌」を歌い、お勤めをする。
最後にフランチェスコは重い皮膚病を患っているものを怖れており
その怖れを克服することを主に誓う。
第3景『重い皮膚病患者への接吻』
フランチェスコは重い皮膚病患者に会い、接吻する。
すると病は癒され、その喜びから踊り出す。
患者はそれまで人生に対して卑屈だったのがよりポジティブに
生きようとする。
第4景『旅する天使』
フランチェスコたちのいる修道院を旅姿の天使が訪れる。
キバラセンニョムシクイ(ジェリゴネ)の囀りが天使の登場を暗示。
天使は修道院にいる修道士たちに「予定説」に関する問いをする。
修道士エリアは問いに答えず天使を追い出し、
再び訪れた天使に修道士ベルナルドは答える。
天使が去ったあと、修道士たちは旅人が実は天使だったことを知る。
(因みに天使は5色の羽根を持っている。
これはサンマルコ美術館にあるフラ・アンジェリコの
『受胎告知』の絵にインスピレーションを得ているらしい。
この絵のリンクはこちら。)
第5景『音楽を奏でる天使』
再び天使が修道院を訪れ、今度はフランチェスコの前に現れる。
天使はヴィオールを奏でるが、このヴィオールは
オンドマルトノの音で表現される。
天使の音楽を聞いているうちにフランチェスコは倒れる。
天使が去ったあと、倒れているフランチェスコを
修道士たちが抱え起こす。
第6景『鳥たちへの説教』
フランチェスコが鳥たちに説教をする。
説教は途中様々な鳥たちの鳴き声で中断される。
そして最後に様々な鳥たちの囀りが一斉に起こる
全曲の中でも最も素晴らしい聴き所となる。
第7景『聖痕』
夜中の山でフランチェスコが祈りを捧げている。
イエス=キリストの受けた苦しみを自分にも分けてほしいと願う。
合唱がイエスの声を表現し、その後5回のクラスターで
イエスの受けた5つの傷がフランチェスコにも表れたことを暗示。
第8景『死と新生』
フランチェスコは「太陽の讃歌」を歌いながら
あらゆるものへの別れを告げる。
フランチェスコが死ぬとヒバリが賑やかに歌い、
最後は感動的な合唱で幕を閉じる。
言葉で書くと難しいようだけれども、
実際に音楽を聴くと、『トゥランガリーラ』でもお馴染みの
メシアン独特のフレーズが登場したり、
鳥たちのざわめきやら、重大なことが起きる時のクラスター音など
音楽的には非常にわかりやすいものになっている。
いや、そのわかりやすさを実現しているのは
やはり何と言ってもメシアンの演奏に精通した小澤さんの棒だろう。
もう随分昔のことなので正確なことは覚えていないのだけれど、
この1983年のパリでの初演の時だったのか、
1986年の日本での部分初演の時のことだったのか、
そのリハーサルの模様が NHK のニュースで報道されたことがある。
その中で、メシアンが小澤さんに注文を付けるのだ、
今のところはそうじゃない、こういう風に演奏してほしい、と。
すると、何と小澤さんは作曲者本人に反論するのだ。
多分、いや、あなたのその意図を実現するには
こういう風に演奏した方がよいのだ、
実際の音にするのは自分の仕事だから自分に任せてほしい、
といったようなことだったように記憶している。
この場面を見て、凄い! と思ったものだ。
小澤さんが楽譜を読み込んで作曲者の意図を理解し、
それを具体的な音にする話は村上春樹さんとの対談に
何度も出て来るけれども、
ある意味作曲者本人ですら想像できていない音が
小澤さんには具体的に聞こえているということではないだろうか。
小澤さんは齋藤秀雄先生から教わったのは、
単に指揮法ではなかった、一番大事なのは、と
「私の履歴書」の中で語っている。
「先生が僕らに教え込んだのは音楽をやる気持ちそのものだ。作曲家の意図を一音一音の中からつかみだし、現実の音にする。そのために命だって賭ける。音楽家にとって最後、一番大事なことを生涯かけて教えたのだ。」
小澤さんが指揮をする時のあの熱い感じは実はここから来ているのだ。
そして、作曲者のメシアン本人にあそこまできっぱりと
物申せるというのは確とした信念があるからだ。
『アッシジの聖フランチェスコ』の録音に聞くのは、
メシアンの音楽への理解と共感、
そして自分自身の信念と情熱の結晶と言えないだろうか。
だからこそ4時間に及ぶ音楽が説得力を持ち、
大きな感動をもたらすことができるのである。
* * *
例によって既に十分長い文章になってしまったけれども、
自分の手許にある小澤さんの CD に纏わる話と
その感想について語るのは一旦これで終わりにする。
終わるに当たって、まだまだ聴いていない、
そして聴いて見たい小澤さんの CD もあることなので、
それについて触れておきたいと思う。
その前にまず、これから小澤さんの演奏を聴いてみたいと
思われる方の為に、日本版「ニューズウィーク」誌の
2024年3月5日号の小澤さんの特集記事にあった
「ニューヨークタイムズ」記者の名盤8選なるものを転載しておく。
・メシアン『アッシジの聖フランチェスコ』1983年パリ・オペラ座管
(初演時のライブ録音)
・ベルリオーズ『幻想交響曲』2014年サイトウ・キネン
(サイトウ・キネン・フェスティバル松本のライブ録音)
・フォーレ『管弦楽作品集』1986年ボストン響
・マーラー『交響曲第1番』1987年ボストン響
・デュテイユー『時間の影』1998年ボストン響
・ストラヴィンスキー『春の祭典』1968年シカゴ響
・チャイコフスキー『白鳥の湖』1978年ボストン響
・リスト『ピアノ協奏曲第1番・第2番/死の舞踏』
1987年クリスチャン・ツィメルマン (pf), ボストン響
今回書いた『アッシジの聖フランチェスコ』を除いては
僕が持っているものとは全く被っていないね。w
というわけで、僕が気になっているディスクは次のものになる。
上のリストにも影響を受けているけれど、録音の古い順に、
・ストラヴィンスキー『春の祭典』1968年シカゴ響
・チャイコフスキー『ロメオとジュリエット』1973年サンフランシスコ響
・ベートーヴェン『交響曲第9番』1974年ニュー・フィルハーモニア管
・デ・ファリャ『三角帽子』1976年ボストン響
・デュテイユー『時間の影』1998年ボストン響
・ブラームス『交響曲第1番』2010年サイトウ・キネン
(カーネギーホールでのライブ。村上春樹さんの激賞で。w)
・ラヴェル『子供と魔法』2013年サイトウ・キネン
(サイトウ・キネン・フェスティバル松本でのライブ)
小澤さんが亡くなってから小澤さんの CD は、
中古でも手に入りにくくなっているけれども
そのうちどこかで見つけたら聴いてみようと思っている次第。
・