SLをはじめて5年が過ぎた2012年の8月、
新しいことを何かしてみようと、
前から構想だけはあった小説を書き始めて、
FacebookとSNSのそんくすに連載してきました。
ゆるゆると書いているのでなかなか進まず、
2年経った現在もまだ完結していません。
読んでいる方も、前の話がどんなだったか忘れてしまうでしょうね。
そんなわけで、今日のレズデーの機会に、
これまで終わっている第 I 部と第 II 部をまとめて公開したいと思います。
完結となる第 III 部はちょうど書き始めたところ、
終わったらまたここに公開しますね。
* * *
Ⅰ
「いい天気だな——。」
エッフェル塔を見上げる公園のベンチで、青く突き抜けるような空にイアン・シャーウッドは思わず一人ごちた。時計を見る。正午。と同時にブーンという音と共に紫色の雲が彼の前に現れる。それはやがて一人の女性の姿となった。
「Hi!」女性ははにかみながらイアンに挨拶する。「お待たせ。」
「全然待ってないさ。」と、イアン。「時間ピッタシ。相変わらずすごいね、ナオミは。」
ふふっと笑いながら、ナオミと呼ばれたその女性はイアンの隣に腰掛ける。そして彼の方には振り向かずにエッフェル塔を見上げると、
「やっぱりパリはいいわね。」
「うん。僕も好きな街の一つだ。」
「こういう場所が世の中にあるんだって思うだけで、どこかほっとするの。」
「そうだね……。」
同意はしてみたものの、ナオミの言葉の裏に何かがある気がして、それがわかるようなわからなようような気がして、以前から気になっていたことを聞いてみる誘惑に駆られた。
「ね。」
「何?」
「君は本当はどの辺(あた)りにいるんだろう?」
「あはは。」ナオミは無邪気とも思える笑いを見せながらやっとイアンの目を覗き込んだ。「知らない方がいいわよ。」
「何故?」
「多分——。」と、ナオミは再び遠い空を見るような目をしながら言葉を選んだ。「少なくとも、あなたが想像しているようなところにはいないわ。それに——。」またイアンの方に振り返りながら、「知ったとして、あたしのところまで来るつもり? まず来れないし、それだけに知ったら絶望するだけよ。」
「何だかおっかないな。」どこかはぐらかされているような気になりながら、それでもどこか大仰なそのもの言いに、イアンは力なく笑って言った。
「おっかないわよ。」と、ナオミ。「だからこうして会ってる方がいいのよ。」
「そうかもね……。」
耳元にあるスイッチを押すとイアンはヘッドギアを取り外した。やはり低いブーンという音がして、パリの風景は一瞬にして消えた。時計を見る。12時45分。随分いろいろと話したように思ったけれど、たったの45分だったのか。
イアンは休憩室を出ると自分の執務室に向かって歩き出した。廊下の窓の外には幾億もの星と、眼下には木星の衛星エウロパの大地が広がっていた。
その恒星間居住空間搬送船——InterStellar Accommodation Carrier、その頭文字をとって、偉大な物理学者とSF作家への尊敬の念もこめてISAC(アイザック)と呼ばれていた——は、ゆっくりとエウロパへと近付いていった。その動きからするとこの船はエウロパを旋回する軌道へと入っていくようであった。
食堂では窓際のテーブルで呆然とエウロパの地表を見つめているイアンの姿があった。
「おい、イアン、大丈夫か?」食事のプレートを持った男がイアンに近付きながら声をかけた。「何だかヤバイ顔をしてるぞ。」
「やぁ、デイブ。」イアンははっとしたように振り返った。
「またあの日本人の女のことでも考えていたんだろう?」
「うん? まぁ、そうだな。」
「お前は顔に出るからすぐわかる。」
デイブはややからかうような調子で、ニヤリと笑って言った。
「デイブ、実はな——。」とイアンは思い詰めた表情で。「この5日間、連絡がないんだ。」
「よせやい。」とデイブ。「まさか、マジになってんじゃないだろうな。相手はどのISACに乗ってるかわからないし、ということはいつかは連絡が途絶えるということだ。それに、相手が本当に人間なのかどうかもわからないぜ。もともとエターナルライフっていうこの仮想空間は、地球上の生活から宇宙船内への生活への、急激な変化によるショックを和らげるために考え出されたものだ。搭乗員の過去の生活に合わせたアバターをボットが創り出してるってことだってあり得るんだぜ。」
「わかってるさ。」とイアン。「わかってる。だけど、今回の場合は違うんだ。何かが起こってるとしか考えようがない。これまでのやりとりを考えると、彼女は急に連絡を絶つようなタイプではないんだ。」
「それで? 一体どうしようというつもりなんだ?」
「デイブ、ちょうどお前に相談しようかどうか迷っていたところだったんだ。」
「何だか嫌な予感がするな。」
「お前はコンピュータのプロだよな。」
「よく知ってるお前がそういう風に言う時は大抵碌なことじゃないな。」
「彼女が最後のセッションの時、どこからアクセスしていたか知りたいんだ。」
「それはつまり——。」デイブは迷惑そうな面持ちになって言った。「月にあるエターナルライフのデータベースサーバに侵入しろと言ってる?」
イアンは黙って頷いた。
「わかってるのか? それは所謂プライバシーの侵害というやつだぞ。しかも、アクセスしてきた場所がわかったとして、どうするつもりだ? その船まで飛んでいくのか? そうしたところで着艦許可がでるかどうかもわからない。仮に入れたとして、どうやって相手を探すつもりだ? どのISACにも数千人単位の人が乗っている——。」
「あとのことは——まだ考えてない。勿論、わかったら駆けつけたい気持ちはあるさ。ただ——今はただ、何か手がかりをつかみたいだけなんだ。なぁ、デイブ、何とかお願いできないか?」
「しょうがないやつだな。不正アクセスはバレたら厳しい処罰が待ってるんだぞ。お前が死にそうな顔してるの見てられないからやってみるけど、礼は高くつくと思ってな。」
「わかってるよ。頼む、デイブ。」
翌日の同じ時間、同じ場所でイアンは待っていた。デイブはおもしろくなさそうな顔をして現れた。
「やぁ、デイブ、何かわかったか?」
「知らない方がいいと思うけどな。」
「わかったのか?」
「落ち着け。わかったよ。でもますます諦めた方がいいと思うな。」
「どこなんだ?」
「地球だよ。どこかの国のISACじゃない。あそこにはもう人は住めるはずがない。お前が探してる相手は、やっぱりボットか何かだと思うよ。」
馬鹿なことは考えるな——デイブはそう言った。お前も俺も、地球のことなんか何もわかっちゃいない——。
が、その馬鹿なことをイアンはやらかした。誰だってそうだ。チャンスが来たらそれを逃す手はない。
月面基地から飛び立った無数のISACは、それぞれがどこか別の恒星系にある惑星を目指すことを期待されていた。それでも、そうしたISACの殆ど最後のグループの一つであるイアン達の乗ったISACの司令官(コマンダー)は、他の恒星系どころか太陽系内にあるこのエウロパという木星の衛星に関心を持ったようだった。最後に太陽系を去る者は、やはり太陽系に——というよりも地球というあの星に——未練を抱く者なのであろうか。
ISACがエウロパの軌道に乗って間もなく、現地調査隊が編成された。20世紀のボイジャー探査機の時代から、エウロパには大気があることや地球に似た環境であることが指摘されていた。本当にここがかつての地球に似た星であるなら、何も見知らぬ恒星系まで行く必要はないではないか。しかも、自分たちがここに降りることを他のISACの誰が知り得るというのだろう——司令官はそう考えたに違いなかった。5機のポッドが母船を離れてエウロパの地表へと降りて行った。
と、その時、1機のポッドが急旋回したかと思うとフルスロットルで太陽の方向に飛び出して行った。言うまでもなく、このポッドには調査隊に選ばれたイアンが乗っていたのだ。
母船の司令室は騒然となった。イアンに引き返すよう無線が飛んだ。イアンは、すみません、行かなければならないところがあるんです、とだけ言い残すとポッドからセイルを繰り出した。セイルは大きく広がると見事に太陽風を捉え、イアンの乗ったポッドはすーっと小惑星の広がる闇へと消えていった。
ポッドは本来、大型の宇宙船であるISACでは小廻りの利かない、短距離での輸送や連絡を目的として設計されている。従って、長距離の航行には本来向いていない。普通に考えれば、木星から地球に向かうのに十分な燃料を積んでいるとは思えない。イアンはしかし、さすがに宇宙で——月で——育っただけのことはあった。最初の噴射で勢いをつけるとエンジンを停止し、あとは慣性と太陽風に任せたのだ。風を捉まえたヨットが海を快走するように、イアンの乗ったポッドの大きな帆は太陽風を孕み、これまで自分たちがISACで木星まで辿り着いたよりも遥かに速いスピードで太陽系を駈け抜けて行った。この分だと3ヶ月もあれば地球に辿り着くだろう。それくらいの酸素はこのポッドにはあるはずだ——。
お前も俺も、地球のことなんか何もわかっちゃいない——再びデイブの声が聞こえた気がした。一人でいるといろんなことが聞こえてくるものだ。そしてその声に答えていたりもする。デイブ、本当にそうだろうか——僕らは何もわかっちゃいないんだろうか? あの星にいたことがないから? そんな時、イアンは思い出すのだった。小学生の時だったか——宿題で地球のことを調べていて出会った衝撃的な表現を——。それは、「青い地球」というものだった。
今思えば、何故学校の先生がそのような宿題を出したかはわからない。というのも、次第に地球の事を語りたがらない人の方が多くなっていったからだ。イアンの両親にしてもそうだ。うんと幼い頃は——特に父親が——地球はこんな所だと話してくれたのが、わくわくして楽しかったことを覚えている。ところがある時から父も母も地球の話題には触れなくなったのだ。
——ねぇ、あなた。
——うん?
——前から気になっていたのだけれど、イアンに地球のことを話すのはもうやめにしない?
——どうした? 何を急に……。
——どこか——新しい星を見つけて、そこで新しい世界を創るのは、イアンやその子供たち、孫やずっとその先の世代でしょ。
——勿論、そりゃそうさ。
——その時に——見たこともない地球の中途半端な知識が、その足枷になるんじゃないかと思って……。
——馬鹿な! 人は自分がどこから来たか、それをちゃんと知らないと生きていけない存在なんだ。それがわかって初めて未来を創れるのが人間なんだ。
——あなたの言ってることはわかる。歴史というものが始まる以前から、どの民族も自分たちの由来を語り継いで来たわ。親から子へ、子から孫へとね。
——そうだとも。その通りだ。
——初めは口から口へ、やがて文字が生まれ、石や木や、動物の皮や、そして紙に記録されるようになった……。
——その通り。そしてその記録——つまり歴史を学ぶということが、それぞれの民族が生きる知恵を発達させてきたんだよ。
——そうね。だけど、これまでの人間と、イアンたちの世代とには、根本的な、大きな違いがあるわ。
——根本的な……大きな違い?
——そう。わからない?
——何だと言うんだ?
——これまでの人間は、いつの時代に生まれても地球という環境を知っていたわ。だから、何百年前の出来事だろうと、何千年前のことだろうと、同じ世界を共有してるの。でもあの子たちは違う。地球を知らないのよ。この月で生まれて、青い空も、海も、森も知らないのよ。それはデータベースにアクセスすれば百科事典的な知識はいくらでも手に入るわ。でも、それは、あたしやあなたが知っていたような生きた地球の知識——私たちが肌で感じ、鼻でその匂いを嗅いで身につけた知識や知恵には及ばないわ。でも、いつか、あの子たちはその中途半端な知識を絶対視して、こうでなければ、って悩む時が来ると思うの。
——ふーむ。
——あたしはそう思うの。かつて人間はこういう所で幸せに暮らしていたって。だからそれをもう一度再現するんだって。けれど、新しく見つけた星で地球を再現することができるかどうかわからない。再現することがいいことなのかどうかも。それより、新しい環境で、その環境に合った、新しい人間の生活を創造することの方が大事なんじゃないかしら。
——うん。君の言うことはよくわかる。でも、それでも、やっぱり自分がどこから来たか、を知っておくことは大事なことなんじゃないかと思う。
——歴史を学ぶのが大事なのは、それが自分たちが目指している未来を創る礎になるからだと思うの。未来が決まるから歴史が決まるの。歴史があるべき未来を束縛してはいけないわ。あの子たちが自分たちの手で未来を築く自由を得た時、歴史は自動的にあの子たちのものになる、あたしにはそう思えるのよ——。
こんな会話が親たちの間で交わされたかもしれない——後になってイアンはそんなことを想像したりもした。そして、それはイアンの両親だけでなく、地球を捨て、月で長く暮らすうちに、そのように考える親たちが次第に増えていったのではないか、と。
そんな状況であったから、先生の宿題は不思議なものであった。けれど、宿題の詳しい内容は忘れてしまった。多分、過去の地球について調べて発表するような内容だったと思う。寧ろ覚えているのは——いろんなデータベースにアクセスしている時に見つけた「青い地球」とか「緑の惑星」という表現だった。月に育ったイアンは地球なら毎日見ていた。だが、それは白い星なのであって、一度も「青い」とか「緑の」と形容できるようなものではなかったからだ。
イアンはすぐに地球の画像を探した。データベースには20世紀から撮影されてきた地球の写真がたくさん見つかった。
——何て美しいんだろう。
正直そう思った。こんなに美しい星が、何故あんな風になってしまったんだろう? イアンは自分もその一部であるエクソダス計画に至る地球の歴史を調べ始めた。
エクソダス計画そのものの萌芽は2030年代にあった。20世紀の終わり頃から地球温暖化ということが全人類的な課題として上げられていた。そして、その最も有効な手段として先進国や資源に乏しい国で推進されていたのが原子力発電であった。火力発電から原子力発電への移行は、廃棄物の量を20万分の1以下に抑えると同時に、消費する燃料も100万分の1で済む。しかし、政治は、半世紀以上に渡って核兵器の恐ろしさを強調し、その恐怖によって国家間の均衡をとることに懸命になり過ぎた。20世紀の終わりから先進国で相次いだ大規模な原子力発電所の事故は世界中の人々を恐怖に陥れた。今更核兵器と発電所とではそのしくみも安全性も違うと言ってみても、人々は納得しなかった。世界各地で原発反対運動が起き、大衆の支持を得るためにどの国の政治家も原発廃絶を謳い始めた。
各国の指導者たちが原発を棄てたのには、もう一つ理由があった。それは、毎年ひどくなる一方の温暖化現象は、ひとり人類の温室効果ガスの排出によるものでないことが、2020年代の終わりにははっきりしてきたからだ。つまり、地球は何百万年というサイクルで、かつてそうであったような灼熱の時代へと遷移してきているということがわかったのだ。そのような大きな地球の変動に、いくら科学技術があるからと言っても、どうして人類が太刀打ちできるだろうか。これに加えて人間は19世紀の産業革命の時から凡そ200年に渡って温室効果ガスを排出してきたのだ。
2030年代のはじめ、世界中の首脳が、一般の人々の知らないところで秘密裡に会合を行った。そして満場一致の議決を得た。それは、全人類を地球から脱出させ、他の惑星に新天地を求めるというもので、聖書『出エジプト紀』の故事に因んでエクソダス計画と命名された。
もっとも、このあたりになってくると、宿題をやっていた頃のイアンにはわからなかった話だ。彼自身がエクソダス計画の一部となっている今でこそ、その全貌を、裏側をも知っていると言えるだろう。何しろ、もう地球は住める環境ではなくなる、そして、その住み慣れた地球を棄てて、未知の宇宙へ旅立つという途方もない話なのである。その計画の実現には数十年というタイムスパンが必要であり、その途中のどこで計画が明るみになっても、世界中でパニックが起こる可能性があり、しかもそのようなパニックはこの計画全体を葬り去ってしまう可能性すらあった。従って、世界中の首脳たちが連携しながらも、事は極めて秘密裡に運ばれたのだ。
全人類を地球から脱出させること——それには最低でも何千人単位で人が生活できる宇宙船がたくさん必要だ。そのような巨大な宇宙船を地球から打ち上げるのはまず無理だし、仮に出来たとして目立ち過ぎる。また、一般人をいきなり宇宙生活に送り込むのも無謀だ。そこで、まず月にエクソダス計画全体を支える基地を建設し、そこで巨大宇宙船の建造を行うと共に、地球からはシャトルで毎回数十人から数百人というレベルの一般人を選び、この基地で宇宙生活のためのトレーニングを実施することになったのであった。
選ばれた人たちは、ある日突然日常の生活空間から月へと連れ去られた。そしてそこで初めてエクソダス計画のことを知らされ、自分たちのこれからの生活についての説明を受けたのだった。勿論、そこで受けた説明について、地球にいる友人たちに話すことも、そして地球に戻ることも禁じられた。だが、そのショックを和らげるものがその頃——2050年代のことだが——までにはもたらされていた。それが各国政府の肝煎りで世界中に浸透していた仮想空間エターナルライフだったのである。
エターナルライフが急速に広まったのはその自由度にあった。姿形も声も、自分が相手に見せたいように変えることができたし、また自分にもそう見えるのであったし、ヴァーチャルリアリティの技術で何もない部屋に自分の思い描く空間を現出することができた。しかもそこに現出した椅子には座ることができ、ベッドには横になることができたのである! ここまで書けば読者にも想像できると思うが、その空間で会う人間——実際には交信相手が送り出しているアバターなのだが——にも質感があり、握手したり抱擁したりすることが可能であり、従って現実の人間と会っていると思えるほど違和感のないものなのであった。
であればこそ、エターナルライフはごく普通の通信手段として急速に普及したのである。手軽さということでは圧倒的にテレビ電話の方が有利に思えたのであるが、それでも多くの人は、
これこそ、各国の政府が期待していたものであった。月面基地が実際に稼働可能となると、計画に従って政府がランダムに選び、指定した家族が次々と月へ連れて行かれた。徐々にではあるが確実に、コミュニティから毎日何家族かが消えていった。しかし人々はエターナルライフの中でコミュニケーションを取り合っていたので、月へ連れて行かれる当事者以外には誰もこのことに気づかないのであった。エターナルライフは、各国政府が国民に気づかれずに全人類を地球から脱出させるというエクソダス計画にとって、不可欠の前提だったわけである。
そしてもう一つ、エターナルライフには大きな特徴があった。そこに映し出される仮想空間は自分でカスタマイズしたものがあることは当然なのであるが、世界中の主な都市や自然が再現されていたのである。このことが月面基地に連れて来られた人々のショックを最小限に和らげる効果をもたらすことにもなった。数十年かけて作られ、人工的に育てられている樹木や草花があるとは言っても、月面基地の生活自体が殺風景なのである。エターナルライフで友人たちと話している時は、自分たちが月で訓練を受けているのだということも忘れ、また地球の姿が日に日に自分たちが慣れ親しんだものではなくなっているという不安や心配も忘れることができるのだった。
そんなエターナルライフは、月生まれのイアンにとっては、地球を知る最大の情報源でもあった。今は二酸化炭素の雲によって一面覆われ、何の魅力もないまっ白な星が、どれだけ豊かな生命と色彩と光とに溢れていたかはエターナルライフにインすることで体感として知り得たのだった。彼はその虜になった。クールなデイヴに言わせれば、幻想の世界にハマってる、ということになる。が、イアンにとってはそれでもよかった。彼はそこに大事な何かを見出していたのだ。
そうだ!——と、司令室の制止を振り切って自分の所属するISACを飛び出し、地球に向かって高速で飛ぶポッドの中でイアンは心に思った。僕がこうすることは最初から決まっていたのだ。全てが偶然ではない。自分が月に生まれて地球の姿を知らないこと、宿題で地球のことを調べて衝撃を受けたこと、月を離れる最後のISACの乗組員に指名されたこと、エターナルライフにハマったこと、そのエターナルライフでナオミという女性と知り合い、彼女が地球にいるらしいとわかったこと——これら全てはつながっている。そしてその全てに通奏低音として静かに流れ続けているものこそ、彼を生かしているある意志ではなかったか——。地球の美しい姿を取り戻したい。
その意志には彼自身今まで気づいていなかった。そう、今気づくまでは彼のこれまでの人生は、あたかも人が作ったドラマをただ漫然と眺めているようなものであった。しかし、気づいた今、彼は自分の内側から何とも知れない大きな力が湧いて来るのを感じていた。デイヴはきっと僕が女のために飛び出したと呆れているだろう。勿論、ナオミのことは心配だし、彼女に会いたい気持ちも強い。だがそれだけではない、彼女のことは彼がこれまで取り組みたいと考えながら実現できずにいたことを思い切って実行するきっかけを——最後のきっかけを——与えてくれたに過ぎないのだ。
今、イアンはこれまでになく満たされていた。その満たされた感覚に浸りながら、高速で小惑星帯(アステロイドベルト)を抜けるべく大きく舵を切った。
(第Ⅰ部おわり)


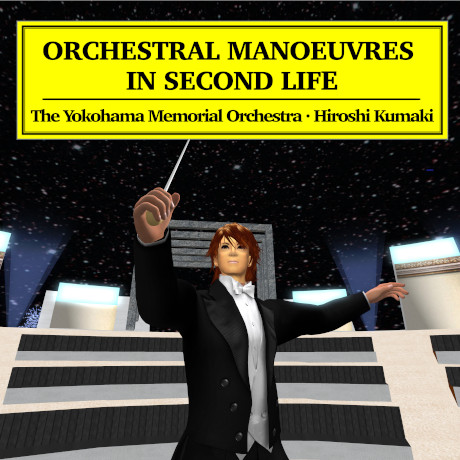




No response to “SL-SF小説・エクソダス2101(第 I 部)”
Leave a Reply