Ⅱ
司令官室へと向かう廊下を歩きながら、デイヴは思った。それにしてもここに住んでいる人間は多すぎるのではないか? この人たちが全員エウロパに移住できるようになるまでにどれくらいの時間が——年月がかかるというのだろう? 或いはそれまで待てずに亡くなってしまう方も出て来るかもしれないではないか。
司令官はエウロパへの移住作戦を進めていたが、同時に母船であるISACはエウロパを回る軌道に乗せたままにしておくことに決めていた。エウロパ移住はまず少数の先発隊がエウロパの地表を調査した上で居住に相応しい地点を特定し、そこに足がかりとなる基地を設営、その基地を居住区として拡張しながら徐々にISACからの人員を受け入れることになっていた。簡単に基地の建設というが、ISACに乗船している二千人からの人間を収容する施設となると、当然のことながらISACそのものを建設するに等しい時間が必要とされる。ならばISACをそのまま上陸させることも考えられるが、ISACは大気圏からの脱出や再突入を考慮して作られた流線型をしたいわゆるロケットではない。恒星間居住区搬送船というその名の通り、巨大な団地と言ってよかった。最初から宇宙空間を移動することを目的として設計されているため、一度地上に降ろしてしまうとそれを再び宇宙空間に送り出すのはまず難しい。この船の司令官は万一エウロパ移住に失敗した場合を考え、ISACが再び別の太陽系を目指して飛ぶことができるよう、エウロパの空に浮かべたままにしたのだった。
「デヴィッド・バーンハイムです。」デイヴがモニターに向かって名乗ると司令官室のドアが開いた。司令官のポール・マイヤーズは軽く会釈するとデスクの前の椅子を指しながら、「座りたまえ。」
「ありがとうございます。」と、デイヴ。
「それで話というのは?」
「他でもない、エウロパ移住の件ですが……。」
マイヤーズ司令官は続けて、という素振りで頷いた。
「エウロパで人が生活できるようになるのは段階的と伺いました。」
「その通りだ。」
「ですが、混乱が起きませんか? 誰しも早く落ち着きたいと焦って……。」
「逆じゃないかな。」司令官は遮った。
「大体みんな保守的なものだよ。変化を好まない。今うまく行っていればそれを敢えて変えようとはしないものさ。特に今回のミッションでは一般人が多く乗っている。彼らは目的もなく、ただ連れて来られただけの人たちだ。大地に降りれるからと言って、競って未知の世界で暮らそうとする人は少ないだろうよ。それに……。」
マイヤーズは間を置いた。「この船は月面基地を離れる最後の船ということもあって、他の船より科学スタッフが多い。幸いなことにね。だから統率には問題ないと思うのだよ。」
「なるほど。」デイヴは応じた。「加えて、ISACそのものを上陸させず、このままエウロパの周回軌道に乗せておくということは、エウロパ上陸にリスクがあることを示しているわけですものね。」
「そうだ。これは暗黙のメッセージなのだ。まだ移住は決定ではない、という。」
「いえ、こういう質問をしたのも、この船には起きている人が多いからですが……。やはり、地球や月に未練がある人が多いのではないかと。であれば、エウロパなんかで危険を冒すよりは、いっそのこと月へ戻ったらどうなんでしょうか?」
ISACはその名の通り恒星間居住区搬送船だ。しかし、二十二世紀初頭のこの頃、人類はまだ一般人が利用できるような恒星間飛行の技術経験に乏しい。恒星間と一口に言うが、最も近い太陽系まで光の速さで4年以上かかるが、そんなに速い宇宙船は未だ開発されてはいない。従って、新しい居住可能な星を求めて月から旅立って行った無数のISACにとって、最初の太陽系に遭遇するまでには数十年単位の時間が見込まれていた。そこで、一般的にはISACを運行する乗務員を除いて、住民は全て冷凍睡眠(コールドスリープ)の状態に置かれるのだった。そして移住可能な星が見つかった時に、コールドスリープは解除される。各ISACの司令官にはその開始と終了のタイミングを決定する権限が与えられていた。
にも拘わらず、マイヤーズ司令官はコールドスリープに入るのは自由とした。デイヴは疑っていた。コールドスリープに入らなくていいということは、目的とする星が近いということだ。とすれば、この司令官は本当は太陽系を出る気がないのではないか、と。そう日頃から思っていたからこそ、月へ戻ったらどうか、と訊いてみたのだ。この司令官はどんな反応を示すだろう?
「月基地はあと半年ほどで使えなくなる。」司令官は冷たく言った。「全てのコンピュータ、ロボット、インフラが停止するからな。」
「やめて下さい。」と、デイヴ。「そんな一般人向けの説明は。僕らは月面基地の科学スタッフですよ。月面基地の全システム停止は単にタイマーがセットされてるからじゃないですか。タイマーさえ解除すれば、月面基地が半永久的に使えることぐらい、スタッフなら誰でも知ってますよ。」
ここでふっとデイヴが思わず鼻で笑ってしまったのは、瞬間あることを思い出したからだ。地球で温暖化が急速に進んだのは全世界的に原子力発電を放棄したことも関係していると聞いている。しかし、その温暖化の進む地球から人々を救い出すためにエクソダス計画の一環として作られた月面基地は原子力をそのエネルギー源としていた。更に、発電により生じた使用済核燃料を再処理する工場もあり、そのプロセスによって半永久的なエネルギー供給が可能になっていたのだ。何と皮肉な話ではないか、と。
「むぅ。」と司令官は唸った。「そうだな。今の私の説明では月に戻れない理由にはなっていないな。確かに一般人向けの説明だった……。」
そこで一呼吸置くと、マイヤーズ司令官はデイヴの目をしっかりと見つめながらゆっくりと話し始めた。
「バーンハイム君……。いいかね、我々人類は短く見積もって文明と呼ばれるものが生まれてから1万年、長く見積もって類人猿と呼ばれていた頃から数えて100万年以上も地球という星で生きてきたのだよ。途方もなく長い時間だよ。」
司令官は少しだけ間を置いた。
「人類は地球しか知らないんだよ。どんな状況のドラマがあったにせよ、常に地球という舞台があった。その舞台の上でこそ、或いは喜び、或いは憎しみ、殺し合うことすらしてきた。でも、突然、その舞台が消えてしまった。地球という舞台のないところで、どうやって生きていったらいいのか、誰も経験したことないし、わからないし、不安でいっぱいだ。だからこそ、この計画では、全ての人間に地球をあきらめさせること、新しい世界をみつけることを強制したんだ。少しでも、ほんのわずかでも、地球に帰れるかもしれない、もしかするとそこで生活できるかもしれないという可能性と希望を絶つ必要があったんだよ。だって、誰だって地球を離れたい人なんていやしない。もしそんな可能性が残っていようものなら、その可能性を巡って人は争い、そして結局は滅びの道を辿る……。」
その目の先に恐ろしいものを目の当たりにしているような険しい表情になりながら、マイヤーズ司令官はしばらく黙ったまま部屋を行き来していた。その厳しい空気に相槌すら打つこともできず、デイヴはただ司令官の動きを見守りながら次の言葉を待った。
「だから、月面基地のその話は禁句だ。絶対にしてはならん。それに——。」
司令官はデイヴの前に来ると、目をぎろりと覗き込むようにして続けた。
「君はさっき、自分たちは科学スタッフだから云々、と言ったが、今言ったような状況を考えた時に、だ。スタッフだから、人ができないことができるから、という理由でそういうことをしていいと思っているのかね? スタッフというのは人にサービスを提供するためにそこにいるんじゃないのかね。スタッフというのは特権階級ではないのだよ。自分にその権限が与えられているからと言って、人より有利なことをしようというのはおかしくはないかね?」
思い当たるところもあってデイヴは思わず司令官から目を反らしてしまった。
「おっしゃるとおりです。申し訳ありません。」
「うん。いや、いい。わかってくれれば。月面基地のことは忘れろ。」
言い過ぎた、という表情をしながら、司令官はデイヴの肩を叩きながら言った。
「実は、俺は軍の経験が長かったが、どこに行ってもそういうのを見て来たし、そういうのが許せなかった。だから、いつも自分の部下にだけは本物のスタッフでいてほしいとそう願ってるだけなんだ。許せ。」
「いえ、自分にもわかります。おっしゃることが。」
「そうか。ありがとう。」
そう行って背を向けたままエウロパを見下ろす窓に寄ったかと思うと急に振り返って。
「だがな、バーンハイム君。」
「はい。」
「スタッフにも許される範囲というのはあるぞ。さっきも言ったように、この計画では誰一人地球や月に残してはならんし、全てのISACは新しい星を見つけに旅立たなきゃならん。そのための恒星間宇宙船だ。だがな、誰も太陽系から離れてはいかん、とは言ってないのだよ。」
デイヴに向かってニヤリと笑うと、再び眼下に広がる木星の衛星に真剣な眼差しを注ぐのだった。
* * *
あれから3日くらい経った時だろうか。母船の司令室から戻って来るようにと執拗に繰り返す無線がぴたりと止まった。いや、実際には5日くらい経っているのかも、逆にまだ1日しか経っていないのかもしれなかった。母船が月からここまで巡航してきた何倍ものスピードで地球に向かっているのだ。イアンに流れている時間は既にデビッドたちの時間とも、また地球の時間とも違っていた。ポッドは高速でただ一向に太陽に向かっていた。だからイアンには昼も夜もなく、一日などという概念はなくなっていた。小惑星帯に入るまでにはまだ時間があり、自動操縦にしていたこともあり、疲れたら寝る、寝るのに疲れたら起きるということが繰り返されていたから、時間の感覚は全くなくなっていた。そもそも、宇宙空間を移動するのに、どうして地球の一日を想定する必要があるのだろう?
司令室からの無線が止まったのは、これ以上イアンの捜索と確保をする労力をマイヤーズ司令官が惜しんだためだろう。1人のスタッフと1機のポッドの損失。そのためだけに、彼のISACに預かっている2000人以上の人間の未来に関わる計画を遅らせてはいけない。どのみちあの若者はここから飛び出していくに違いない……。
奇妙なことに、司令室からの無線が止まったのと入れ替わるように、デビッドからの無線がよく入るようになった。彼もまた落ち着いたということなのだろうか。最初は、お前のせいで毎日質問責めだったと愚痴や嫌みも多かったが、そのうちだんだんいつもの二人の会話に戻ってきた。そんなある時、突然思い出したようにデビッドは話し始めた。
「そうそう、お前に言わなきゃと思いながら、ずっとそのままになってたことがあったよ。」
「何だい?」
「イアン、お前に頼まれて、ナオミさんがインしてる元を調べた時のことだけど。」
「うん。」
「記録にはそのサーバのOSも出ていたんだ。」
「うん。」
「それが驚いたことに、JUNOS(ユーノス)だったんだよ。」
「というのは?」
「ああ、やっぱり知らないか。」
「うん。何、それ?」
「JUNOSというのは日本でUNIXを元に開発されたOSなんだけれども、つまり、日本人というのは漢字を使うだろ? で、あいつらに言わせると、俺たちには同じに見える漢字でも、日本で使ってるものと中国や韓国で使ってるものは違うらしいんだ。そういうのも入れると漢字というのは5万字以上あるらしい。」
「うわ。それ覚えるの無理だな。」
「無理だな。が、ともかく、それだけの文字を扱えるOSの開発が進められ、その副産物として、世界中の文字が扱えるOSとして進化したわけだ。お前が聞いたこともない言語の見たこともないような文字も扱えるってわけだ。」
「俺には必要ないな。」
「ところが、それだけの文字体系を扱えるようにするというところから、複雑系をインプットにして処理させるシステムへと開発は進んで行き、当然、計算のためのOSのアーキテクチャは全て見直されて、最終的には世界で一番複雑な計算を高速で行えるOSが出来上がったというわけさ。」
「ふ〜ん。」
「そこで、当初は日本人向けのOSという意味で Japan UNix Operating System の頭文字をとって JUNOS と呼んでいたのが、最終的には JUdgment Navigation and Optimization System、つまり「判断最適化システム」と呼ばれるようになったんだ。」
「へぇ〜。」
「おもしろくなさそうだが、もうちょっと我慢してくれ。このJUNOSというのを開発したのが、実はタチバナ教授という人なんだ。」
「え? タチバナ?」
「そう。タチバナ。」
「ナオミと同じファミリー・ネームだ。」
「うん。そして、実は、地球温暖化は止められないという報告をして、世界各国がエクソダス計画に踏み切るきっかけとなったのが、そのタチバナ教授がJUNOSを使って解析した結果だったんだ。最初こそ彼は失笑を買ったものの、結局はアメリカ、EU、ロシア、インド、中国各国のスーパー・コンピュータがJUNOSの解析結果を追認する結果を出したってわけさ。そこで各国政府は本気にこの計画を考え始めたわけだな。」
「なるほど。それで、その後その教授は?」
「彼は地球を棄てて宇宙に活路を見出すというエクソダス計画には反対していたんだ。そこで研究を続けて5年後に、新しい研究結果を元にエクソダス計画の変更を訴えた。」
「が、相手にされなかったわけだな。」
「そう。もう計画はスタートしていたし、各国の威信がかかっているからね。これまで一度として意見が一致したことのない世界の国々が奇跡的とも言える合意を成し遂げたプロジェクトだもの。余計な雑音を入れなくはなかったんだね。」
「それで?」
「それ以降タチバナ教授も、彼のJUNOS搭載のスーパーコンピュータも行方不明になってるね。」
「もしかするとナオミは……。」
「タチバナ教授の娘さんか、少なくとも何か関係のある人のような気がするね。」
「夢を見たんだ」と、ある時デイヴが言って来た。
「とても現実的な夢さ。僕は光と温度を感じてコールドスリープから覚めるんだ。近くに人類が生息可能な惑星を見つけてコンピュータがスタッフを起こしたというわけさ。計器を見ると1300年が経過していた。1300年だよ。その間僕らの船は適当な星を見つけることができずにずっと宇宙を彷徨っていたというわけさ。
「1300年か……。コールドスリープはそんなに持つのかな。」と、イアンが口を挟む。
「さぁね。一応、生理学的には500年は保証されてるって聞いてるけど、あくまで机上の計算だからね。でも、今の僕らの科学では光を超えて航行することは不可能なわけだから、現実に1000年経っても新しい星が見つからないということはありそうだな。」
今度はイアンは答えなかった。ありそうなことだ、と彼自身思った。が、今デイヴたちがエウロパで行っている生存検証の結果が否定的なものとなった場合、そのありそうなことはデイヴにとっては他人事ではなくなるからだ。簡単に相槌は打てなかった。
少しだけ待ってデイヴは続けた。
「で、話を戻すと、呼ばれたスタッフが司令室に集まると、スクリーンには、白い、大気も海もない星が映し出されていたんだ。とてもその星自体は生存可能には思えなかったのだけれど、コンピュータが何らかの判断を下したわけだから一応調査をしようということになって、数人がポッドで地表に降りることになったんだ。その中には僕も入っているんだけどね。
「ポッドは暫く周辺の地域を飛んで回ったんだけど、そのうち、人工構造物を見つけたんだ。そこでみんなで降りて行って、その構造物を調べてみることにした。
「それは恐らくかつてここにいた生命体——多分、僕らと同じようなヒューマノイド型と思われる生命体——が建設した何かの施設の廃墟のようだった。そう、ヒューマノイドだと思ったのは、どことなくその廃墟に懐かしさを覚えたからだったんだよ。施設の奥に進むにつれて、その懐かしさはだんだん増してきたんだ。そのうち、メンバーの一人が埃まみれの壁から文字らしきものを見つけた。埃を払うと、驚いたことに僕らにはその文字の意味がわかったんだ。何故だと思う?」
「何故だろうね?」と、イアン。
「英語だったんだよ。」
「ん?」
「僕らは驚いて更に足を進めた。それも、ある確信を持って。もしかして、この廊下をこっちに進めば、って。そしてその通り見つけたんだ。僕らがかつていた司令室を。僕らは驚きのあまり立ち尽くしていた。その時、司令室の大きな窓にぱぁっと光が差して来て、緑色の大きな星が昇って来たんだよ。」
「ということは——。」
「そう。僕らが見つけた星は月で、廃墟は月面基地だったというわけさ。」
「なるほど……。」
「でもさ、これもまたありそうなことと思わないかい、イアン? 新しい星を目指して遠くへ遠くへと散らばっていった無数のISACのうち何れかが、やがて再び月や地球に辿り着くってこと……。」
「そうだな……。」イアンは感慨深そうだった。
「でもね、その時、僕の夢にあったように、全てが廃墟と化していたら、すごく悲しいと思わないかい? マイヤーズ司令官はみんなの地球や月へ戻りたいという気持ちを断ち切るために、あと半年もすれば月面基地は全機能を停止すると言ってるけど……。」
「当初の計画通りだな。」
「けれど、今戻るんじゃなくて、長い旅の末に辿り着くこともあるわけじゃない。その人たちのことを考えると——自分も含めてだけど——何とかならないものなのかな。」
「何ともならないだろうけど——。」とイアンは言った。「ただ、僕が君の夢に何となく希望を感じたのはその最後の部分さ。」
「最後の部分?」
「君の夢は地球の出で終わってる。その地球は緑に光っていたと言ったよね。そのことさ。僕らは白い地球しか知らない。1300年経って、もし地球が緑に輝く星に戻っているなら、たとえ月の基地が廃墟になっていたとしても、僕らはもう一度地球でやり直せる、そんな希望を僕は感じたんだ。」
「なるほどね。」とデイヴ。「だけど、どっちにしても、僕はこのプロジェクトは、何か根本から間違っているような、そんな気がするんだ。」
「とても現実的な夢さ。僕は光と温度を感じてコールドスリープから覚めるんだ。近くに人類が生息可能な惑星を見つけてコンピュータがスタッフを起こしたというわけさ。計器を見ると1300年が経過していた。1300年だよ。その間僕らの船は適当な星を見つけることができずにずっと宇宙を彷徨っていたというわけさ。
「1300年か……。コールドスリープはそんなに持つのかな。」と、イアンが口を挟む。
「さぁね。一応、生理学的には500年は保証されてるって聞いてるけど、あくまで机上の計算だからね。でも、今の僕らの科学では光を超えて航行することは不可能なわけだから、現実に1000年経っても新しい星が見つからないということはありそうだな。」
今度はイアンは答えなかった。ありそうなことだ、と彼自身思った。が、今デイヴたちがエウロパで行っている生存検証の結果が否定的なものとなった場合、そのありそうなことはデイヴにとっては他人事ではなくなるからだ。簡単に相槌は打てなかった。
少しだけ待ってデイヴは続けた。
「で、話を戻すと、呼ばれたスタッフが司令室に集まると、スクリーンには、白い、大気も海もない星が映し出されていたんだ。とてもその星自体は生存可能には思えなかったのだけれど、コンピュータが何らかの判断を下したわけだから一応調査をしようということになって、数人がポッドで地表に降りることになったんだ。その中には僕も入っているんだけどね。
「ポッドは暫く周辺の地域を飛んで回ったんだけど、そのうち、人工構造物を見つけたんだ。そこでみんなで降りて行って、その構造物を調べてみることにした。
「それは恐らくかつてここにいた生命体——多分、僕らと同じようなヒューマノイド型と思われる生命体——が建設した何かの施設の廃墟のようだった。そう、ヒューマノイドだと思ったのは、どことなくその廃墟に懐かしさを覚えたからだったんだよ。施設の奥に進むにつれて、その懐かしさはだんだん増してきたんだ。そのうち、メンバーの一人が埃まみれの壁から文字らしきものを見つけた。埃を払うと、驚いたことに僕らにはその文字の意味がわかったんだ。何故だと思う?」
「何故だろうね?」と、イアン。
「英語だったんだよ。」
「ん?」
「僕らは驚いて更に足を進めた。それも、ある確信を持って。もしかして、この廊下をこっちに進めば、って。そしてその通り見つけたんだ。僕らがかつていた司令室を。僕らは驚きのあまり立ち尽くしていた。その時、司令室の大きな窓にぱぁっと光が差して来て、緑色の大きな星が昇って来たんだよ。」
「ということは——。」
「そう。僕らが見つけた星は月で、廃墟は月面基地だったというわけさ。」
「なるほど……。」
「でもさ、これもまたありそうなことと思わないかい、イアン? 新しい星を目指して遠くへ遠くへと散らばっていった無数のISACのうち何れかが、やがて再び月や地球に辿り着くってこと……。」
「そうだな……。」イアンは感慨深そうだった。
「でもね、その時、僕の夢にあったように、全てが廃墟と化していたら、すごく悲しいと思わないかい? マイヤーズ司令官はみんなの地球や月へ戻りたいという気持ちを断ち切るために、あと半年もすれば月面基地は全機能を停止すると言ってるけど……。」
「当初の計画通りだな。」
「けれど、今戻るんじゃなくて、長い旅の末に辿り着くこともあるわけじゃない。その人たちのことを考えると——自分も含めてだけど——何とかならないものなのかな。」
「何ともならないだろうけど——。」とイアンは言った。「ただ、僕が君の夢に何となく希望を感じたのはその最後の部分さ。」
「最後の部分?」
「君の夢は地球の出で終わってる。その地球は緑に光っていたと言ったよね。そのことさ。僕らは白い地球しか知らない。1300年経って、もし地球が緑に輝く星に戻っているなら、たとえ月の基地が廃墟になっていたとしても、僕らはもう一度地球でやり直せる、そんな希望を僕は感じたんだ。」
「なるほどね。」とデイヴ。「だけど、どっちにしても、僕はこのプロジェクトは、何か根本から間違っているような、そんな気がするんだ。」
時間を持て余すと人は普段気づかないことに気づいたりする。ある時イアンは何百と並ぶスイッチや計器の類をぼうっと眺めていて、ふとエターナルライフのランチャースイッチがあることに気づいた。
ポッドにそのエターナルライフの機能が装備されていることには何の不思議もなかった。地球では勿論のこと、月面基地でも一般人にとってはエターナルライフは普通のコミュニケーション手段だったからだ。が、月面基地のスタッフにとって、お互いの連絡は映像のない、音声のみで済ませることが普通だった。イアンとデイヴにしても、知り合った子供の頃はエターナルライフを使っていたが、一緒に働くようになってからは無線でのやりとりが普通になっていた。イアンにISACに戻るよう呼びかける通信に始まり、その後のデイヴとのやりとりもずっと無線で交わしていることに、これまで何の違和感も感じていなかったのだ。デイヴと話すのに敢えてエターナルライフを起動することなんて思いもしなかった。それだけに、ごく当たり前にエターナルライフのランチャースイッチがコックピットに装備されているのに気づいた時には、何だか笑えてくるのだった。
つれづれに任せてイアンはスイッチを押してみた。システムが素早く網膜認証を行ったかと思うと、ブーンというあの懐かしい起動音と共に仮想空間が彼の周りに現出した。最後にログアウトしたパリの風景だった。
その時!
イアンは視線の先に一人の女性の姿を捉えた。と、次の瞬間、その女性は姿を消した。あ、と思う間もなかった。間違いない。ナオミだ。もう少し早くログインしていれば、何か話ができたかもしれないのに……。彼女は自分に気づいただろうか? 今となっては誰も人がいるはずのないエターナルライフだ。気づかないはずがない。とすれば、もう一度ログインして来るだろうか?
イアンは視線の先に一人の女性の姿を捉えた。と、次の瞬間、その女性は姿を消した。あ、と思う間もなかった。間違いない。ナオミだ。もう少し早くログインしていれば、何か話ができたかもしれないのに……。彼女は自分に気づいただろうか? 今となっては誰も人がいるはずのないエターナルライフだ。気づかないはずがない。とすれば、もう一度ログインして来るだろうか?
気づいていればきっともう一度入ってくる。そう信じてイアンは彼女が消えた辺りをうろうろと歩きながら待った。五分経ち十分が経過した。が、ナオミがインしてくる気配はどこにもなかった。やっぱり気づかなかったのだろうか? それとも、気づいてはいたのだけれど、僕と会いたくないのだろうか? 少なくとも今は? 待ちながらも悶々とした思いが募るイアンだった。
いや待て、もしかして――。違う場所にいるかもしれないではないか。
「フレンド・リスト、オンライン・オンリー!」イアンが言うとHUD(ヘッドアップ・ディスプレイ)にオンライン中のフレンドの名前が表示される。悲しいことにやはりナオミの名前はなかった。が、一人オンライン中の友達がいる……。
「フレンド・リスト、オンライン・オンリー!」イアンが言うとHUD(ヘッドアップ・ディスプレイ)にオンライン中のフレンドの名前が表示される。悲しいことにやはりナオミの名前はなかった。が、一人オンライン中の友達がいる……。
「デイヴ?」そう言えば、エターナルライフの中でデイヴをあまり見かけたことがなかったことを思い出した。人に本当はロボットかもしれない彼女と仮想空間でデートしてるとイアンをからかうデイヴだっただけに、彼がここにいるのは意外だった。
「地図に表示!」HUDの地図がスクロールしたかと思うとタンザニアSIMが表示された。その中に友達を示す黄色い点が1つだけぽつんとある。
「テレポート!」
一瞬にして風景が変わり、いきなり目の前にサファリハットを被った浅黒い男が現れた。イアンはテレポート先に友達を選んだのだ。とすれば、見覚えのないこの男が誰かは、彼にはすぐわかる。
驚いたのはデイヴの方だ。何と言っても突然目の前にイアンが現れたのだから。その姿を見てか、イアンはいきなり笑い出した。
「いやぁ、君にこんな趣味があったとはね。」と、イアン。
「失礼な奴だな、いきなり現れて笑い出すとは。」と、デイヴ。
「ごめんごめん。」イアンが返す。
無理もなかった。現実のデイヴは色白で、体型も少し太っていたから、このエターナルライフにいる彼とは真逆と言ってよかった。
「趣味って言ったけど」と、デイヴ。「そうだね、僕はこういう方が好きさ。僕らは月で生まれただろう。だから地球のことはライブラリでしか知らない。でも、そのライブラリで僕はどれだけ多くの生命が地球に溢れていたかを知ったんだよ。君もそうだと思うけど。」
イアンは静かに頷いた。
「地球って何て素晴らしい星だったんだろう、って思ったのさ。今はエターナルライフの中だけだけど、このタンザニアという国があったところは、本当にたくさんの動物や鳥や植物や、いろんな生命に溢れていたところだったんだ。だからよくここに来てはいろんなことを学ぶんだよ……。」
デイヴはそこで言葉を切って少し黙った。そこから先を言うかどうか躊躇っているようでもあった。イアンは黙って彼は言葉を継ぐのを待った。
「イアン、どうして僕らはこの地球を捨てたんだろうねぇ。地球だけでなく、そこに住む多くの生き物たちを捨てたんだろうねぇ。何故、エクソダス計画にはこうした多様な生命が含まれなかったんだろうか。僕らはエクソダスの申し子みたいに、生まれた時から月で、人間以外に生命のいないところで育って、エクソダスの全てが何の疑いを挟む余地のない、それを大前提として生きてきた。でもさ、そもそも何で地球を捨てる必要があったんだろう? エクソダスって難しいラテン語だけど、要は逃げるってことだろ? 何で逃げる必要があったんだろう? 「出エジプト記」、あれは、イスラエルの民にとっては、エジプトは故郷ではなかったし、そこにあったのは奴隷の暮らしだったから逃げ出したんだ。でも、僕らにとって地球はそうじゃない。故郷じゃないか。だとすれば学ぶべきは危機を前にしてあらゆる生命を救おうとしたノアの方舟じゃないのか? エクソダス(出エジプト記)でなく、ジェネシス(創世紀)計画であるべきでなかったのか?」
デイヴは興奮していた。一気に喋った。そしてまた急に黙った。やがて、ゆっくりと話し始めた。
「イアン、いるかいないかわからない女を追いかけていきなり死の星地球に向かった君は気が狂ってるよ。だけど、僕にはその気持ちはよくわかる。そして、きっとマイヤーズ司令官もだ。あの人もいつか地球へ帰る気でいる。だからこそ、他の司令官が命令通りに太陽系を離れたのに、彼は木星なんかでうろうろしてるんだ。うろうろと言っちゃ悪いか。彼は全く太陽系から出る気がないね。一番最後の船だもの、命令を破ったからってどんな制裁があるかってね。だから、今更だけど、僕はあの人について行く気になったのさ。どのくらいかかるかわからない。でも、きっと僕らは地球に戻る。その時まで待っていてほしいな……。」
イアンは黙って頷いた。目に涙が浮かんでいた。デイヴの気持ちはよくわかる。子供の頃見たライブラリの美しい地球のビデオが頭の中でプレイバックされていた。そして今この瞬間も自分が載ったポッドはその地球を目指しているのだ。
「また、ここに来ていいかい?」やっとのことでイアンは言った。
「勿論さ。」と、デイヴ。「尤も、いつも僕がいるとは限らないけどね。」
「うん。」と、イアン。「またね。」
「また。」と言ってデイヴは姿を消した。イアンもまたログオフボタンを押して、タンザニアの風景は一瞬にして暗いコックピットに戻った。
イアンの視界の先には小さく火星が見えていた。地球はその先だ。もうすぐだ。イアンは深い溜息をついた。
仕事をしている人にとっては――いや、生活というものを営んでいる人にとっては、3ヶ月や6ヶ月という月日はあっと言う間に流れてしまうだろう。同じような繰り返しの中で、今日は特にこれを成し遂げたという実感もないままに、時間がどんどん過ぎていくのだ。イアンにとってもそれは同じだった。与えられたミッションをこなしていた間は。しかし、地球へと向かうポッドの中で、彼には日々こなすべき仕事というのはなかった。ミッションがなかったというのは正確ではない。何故なら彼にとっては、地球に向かうことそのものが自分に与えたミッションだったから。
することがないということは何と苦痛なことなのだろう。嘗て、パスカルは人が仕事をしたり戦争をしたりするのは気を紛らわすためだと書いた。もしそういうことをしなければ、人は自分自身と向き合い、自分の人生――存在――について、そして死について考えなければならなくなる。どんな人にも必ず死は訪れる。この最も確実なことをこそ人は真剣に考えるべきであるに違いない。不確実なことに人生を賭けるよりも。しかし実際には、この最も確実なことから目を逸らしたがるのもまた人間だ。この世に生きている人が誰も経験したことのないということが死に対する不安を呼び起こすのだ。死を考えることは不安だ。そしてこの不安から逃れるには、考える時間を持ってはいけない。自分をとことん忙しくしておく必要があるのだ――。
あの日以来、イアンはエターナルライフにログオンすることが多くなった。もしかしてデイヴやナオミがインして来るかもしれないではないか。その可能性に賭けて殆どログインしっ放しの状態が続いた。彼のコックピットはパリだったりタンザニアだったりした。現実の風景を気にする必要はなかった。今太陽系のこの空間を飛んでいるのは彼以外にいるはずもなく、また、景色は殆ど変化がなかった。小惑星帯(アステロイド・ベルト)を抜けてからは隕石のようなものと遭遇する確率も殆どなくなった。だが、それほど長い時間インしていても、なかなか二人が入って来ることはなかった。そしてこの時、イアンは、実は気が狂いそうなほどに広い太陽系という空間の中で、自分にはこの二人より友達らしい友達がいないことに今更のように気づいた。しかもそのうち一人は本当に人間なのかどうかもわからない――。
やがて、待つ時間が長くなると、イアンはエターナルライフ内に再現された地球にあったという世界中の都市や雄大な自然を巡る旅を始めた。デイヴの言う通りだ。その旅を通じて、イアンはいかに地球が素晴らしい星であったかを改めて知らされたのだ。だが、その何百もあるSIMの驚異的な旅も、何日もしないうちに終えてしまったのだ。時間の流れるのが何と遅いことだろう。
次に彼が手を出したのはライブラリーだった。
「司書(ライブラリアン)!」と彼が発すると、ライブラリ担当のアプリケーションが返事をした。読みたい本の書名を言えばその本――と言っても勿論電子媒体だが――を出して来てくれるし、書名を知らなくても、これこれこういう本と大体のイメージを告げると、それではこういうのはどうでしょう? と次から次へと彼の希望に叶いそうな本を薦めるのである。これが実はよかった。コンピュータとは言え、自分とちゃんと会話してくれる相手がいるということはありがたいことだ。
このライブラリアンは IRIS(アイリス)、つまり Integrated Request Interpretation & Solution Service(統合型要求解釈解決システム)と呼ばれる対話型要求遂行システムの一部だった。IRIS は、膨大な人類知のデータベースであるライブラリアンの他、宇宙船の運航を司る航海士(ナビゲーター)、大気や物質の成分などを分析する分析官(アナリスト)といったそれぞれ専門のアプリケーション群で構成されており、そのバックグラウンドでは常に心理士(サイコロジスト)と呼ばれるアプリケーションが動いており、人間が発する言葉から、その背後にある真の要求を察知して――つまり、言われた内容が真に文字通りのことを意図しているのか、皮肉で言っているのかも識別して――、その情報を他のアプリケーションに受け渡す働きをするのである。これら専門的アプリケーションとサイコロジストの連携プレーによって、普通の人間の会話に特有な曖昧な表現であっても、コンピュータは的確にその人の要求に応えることができるようになったのである。目的がはっきりしている場合には、恰も人に話しかけるように「ライブラリアン!」「ナビゲーター!」と呼びかければそのアプリケーションを直接呼び出すことができたし、どのアプリケーションに相談してよいかわからないような時にはそのまま、「コンピュータ!」と呼び出せばよいのだ。21世紀の初頭には、この IRIS を逆さまにしたような秘書アプリケーションもあったが、その頃とは比較にならない程コンピュータは人間のことを理解するようになっていたのである。
そんなライブラリアンの薦めに従って、彼はいろんな本を読む機会を得た。先ほどのパスカルだってそうだ。こんな時でもないと哲学書なんか読む気にならなかったかもしれない。そう言えば、パスカルが『パンセ』を書いたのは牢獄の中だった。彼もまた考えること以外、何もすることがなかったのだろう……。哲学書から歴史書、そして、いつかのデイヴの言葉が気になって、改めて聖書にも目を通した。そこから、世界の様々な民族が描いた天地創造の物語も読み漁った。我々人間はどのように始まり、そして終わっていくのか――それは、世界の諸民族に共通のテーマだ。
こうした本を読みながら、イアンは今自分がそこにいることの意味を考え始めていた。自分はこれから何をしようと言うのだろう、と。だが、そのような難しいこと――本質的なこと――を考えることはそう続くものでもない。集中してものを読み、考えているつもりでもいつの間にか眠りに落ちていることがあったし、眠りから覚めてはまた本に――ディスプレイに――向かうという繰り返しが続いた。
その繰り返しのうちに――やがて、白く小さな2つの星が見えてきた。それこそ紛れもない、地球とその軌道を回る月の姿だった。イアンは自分の旅が終わりに近付いていることを知った。
(第 II 部おわり)


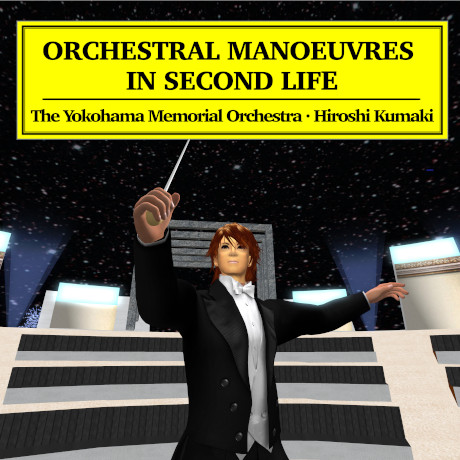




No response to “SL-SF小説・エクソダス2101(第 II 部)”
Leave a Reply