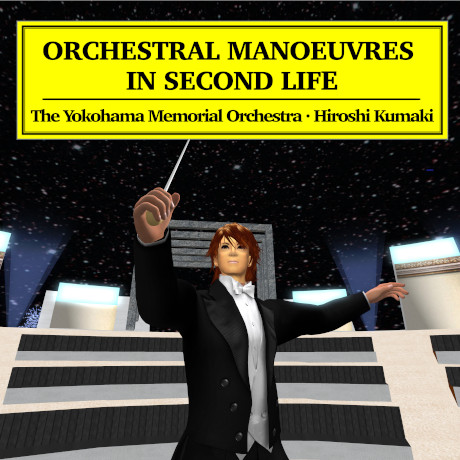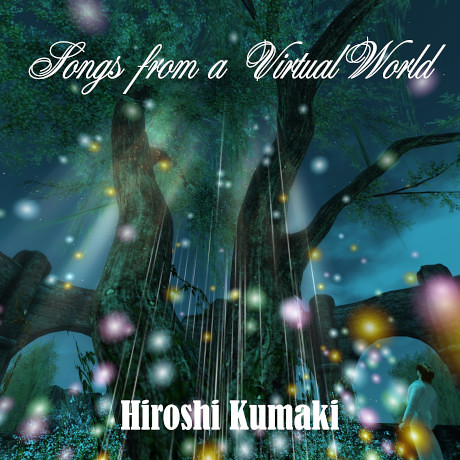今年のバーニング・マンのアートテーマは
「Tomorrow Today」で、ユートピアでもなく
ディストピアでもなく、その中間の持続可能な未来を
自分たちの力で実現させよう、というもの。
僕自身は、それは可能なことだと考えています。
一つには、19世紀の産業革命以来、科学は進歩して来たのだけれど
その当時もそして今も、「その」科学は人間の生活を
ある程度便利にしたかもしれないけれども、
地球上の生命にとっても地球そのものにとっても、
そして人類自身にとっても、よくない影響を与える科学でした。
それは本来の科学ではないのではないか?
本来の科学はもっと人間の生活も地球環境も
豊かにするものだったのではないか、と思うのです。
先日「ラムセス大王展」に行って来たことを書きましたが、
僕が古代エジプトに惹かれるのは、
あの、現代の技術を以てしても難しいと言われるピラミッド、
あのピラミッドの建設には、現代と異なる別の科学が
使われたのではないか? という想像です。
例の、グラハム・ハンコックの『神々の指紋』を読むと
今から1万500年ほど前に地球規模の大洪水、
ノアの洪水と思しき大洪水が起こり、
それまでに存在していた高度な文明が全て破壊され
それらの文明の科学技術をあまり知らない生き残りが
再出発してできたのが今の私たちに至る文明だと言うのです。
それは、あり得る話だと僕は考えていますし、
そうだとすると、その失われた文明こそ、
本来の科学だったのではないか、
そして、かつて存在したものならば、
もう一度それを取り戻すことができるのではないか、と。
古代エジプトは何千年という遠い昔の話ですが、
もっと近いところでは、20世紀の初めに電気を巡って
トーマス・エジソンとニコラ・テスラが競ったことがあります。
エジソンの方がテスラよりも有名で、
テスラと言っても自動車しか思い出さない方が多いでしょうが、
この方も様々な発明をした科学者で、
電気を伝えるのに、エジソンは電線を使いましたが、
テスラは大地や空気を媒体として電気を伝える方法を
実験していました。
電線はその敷設に空間も費用も掛かりますし
それが設置された場所にしか送れないという制約がありますが、
大地や空気を通して送るとなると、送電コストは安くなり、
また、どこにいても電気が使えるというメリットがあります。
実際、テスラは大地を媒介とする方法については
実験を成功させていて、これは現代の科学者も
テスラと同じ実験をして成功させています。
一方の空気を媒介とする方については、電気を送るための
タワーをテスラは建設しようとしていましたが、
テスラに可能性を感じて出資していた J・P・モーガンは
これが実現すれば電気によるお金儲けができなくなることを案じて
資金を引き揚げ、タワーを壊してしまったと聞きます。
よりお金がかかり、それ故にお金儲けができる
エジソンの技術が支援を受け、現代の私たちの生活に
つながっているというわけです。
ここでも、もしテスラの実験が成功して
それが実現していたら、僕らの生活はもっと違うものになっていた
可能性があるということです。
もう一度古代文明の話に戻ると、
ピラミッドのあの形、四角錐のあの形はベンベン石と呼ばれていて
世界各地のピラミッドだけでなく、やはり世界各地に残る
オベリスクのトップを飾るものでもあります。
古代文明の研究者の中には、これらのピラミッドやオベリスクは
互いにエネルギーを送受信する基地だったと考える人もいて
それはテスラがやろうとしていたことと被ります。
案外、テスラはその古代文明の秘密を知ってしまったのではないか。
そしてそれ故に、その偉大な文明の復活を怖れた人々から
消されてしまったのではないか?
そんなミステリーじみた陰謀論じみたことも
考えたくなってしまいます。
ピラミッドの建設には莫大なエネルギーを要したでしょうが、
エネルギーと言えば思い出すのがアインシュタインの公式
E = mc²
です。
これは、エネルギーと質量とは等価であるということを
示した式で、この式が語っていることは奥が深いと感じています。
つまり、この式が示すのは、エネルギーから物質が産み出せるとも
物質からエネルギーが抽出できる、とも解釈できるからです。
原爆や原発はこの式から導かれる核分裂を使って実現されています。
核分裂とは反対の核融合を使えば莫大なエネルギーが
産み出されるはずですが、現段階ではまだまだ
実用レベルにはなっていないというのが実情です。
実は同じ核爆弾でも水爆はこの核融合のしくみを使っていますが、
そのためのエネルギーを得るのに核分裂を利用するという
中途半端な行き方になっています。
私たちにとって核融合の最も身近な例は太陽です。
あそこで起こっていることが核融合なのです。
何十億年にもわたって遠い星にまでエネルギーを発し続ける
太陽こそ夢の永久機関のように思われますが、
果たして私たちはいつそれを技術として
利用できるようになるのでしょうか?
それとも、やはり古代エジプトや大洪水以前の文明は
核融合の技術を既に持ち合わせていて
その技術を使ってあの巨大なピラミッドに代表される
建築物を築いたのでしょうか?
アインシュタインの E = mc² は
どのように使うかで全く異なる技術をもたらすものと考えます。
そのように、もう一つの道がある、少なくとも可能性がある
ということがわかれば、このまま進めば暗い未来も
もう一つの道を歩めば明るい道が開けるのです。
そんなことを夢想しながら、今年の Burn2 では
どんな音楽を披露しようかと、日々ニヤニヤしている
ヒロシなのであります。