昨日はピアニストのラーザリ・ベルマンのことを書いたけれども
その流れで今日はウラジミール・ホロヴィッツについて
書いてみようと思う。
これは、2年くらい前だったかあるピアニストの方から
「ホロヴィッツは好きですか?」と聞かれて
返事に困ったことがあるからだ。
その時僕はホロヴィッツの演奏のとんでもなく凄いことを
きっと熱く語っていて、それを黙って聞いていた彼女が
その質問をしたのだと思う。
返事に困ったのは、好きとか嫌いとか、
そういうレベルの話ではないからなのだ。
僕が初めてホロヴィッツと意識して聴いた演奏は
例の、1951年の『展覧会の絵』のライヴ録音で、
これはもう、出だしの「プロムナード」からぶっ飛んでしまった。
何と言う迫力!
それまでアシュケナージの寧ろ美しい演奏で聴いて
どこか物足りなさを感じていた僕は
たちまちこの演奏に魅せられてしまったのだ。
一瞬たりとも聴き手を飽きさせない、
グイグイと引っ張っていく演奏。
最後のバーバ・ヤーガからキエフの大門に至る盛り上げ方は
ハンパでなく、エンディングは元の楽譜にはない
ホロヴィッツが即興的にだろうか、沢山の音が追加されているのだ。
これには呆れてしまった。
これは原曲通りではない、しかし無視できない演奏、
ムソルグスキーらしさを最も実現した演奏と言えまいか!
その後、『展覧会の絵』については、
1958年にスヴィャトスラフ・リヒテルがソフィアで行った
コンサートの演奏が素晴らしいと聞いて、これも買って聴いた。
確かにこれも凄い演奏だ。
というのも、こちらは楽譜通りに弾かれているにも拘わらず
ホロヴィッツとはまた違った迫力のある、感動的な演奏なのだ。
僕は、最初に聴いたアシュケナージの演奏は
楽譜通りだからつまらないのだと思っていたが、
リヒテルのこれを聴いて考えを改めた。
楽譜通りでも、演奏家によってその表情は大きく異なる、と。
かくて僕の中で理知的な演奏のリヒテルと
情熱的な演奏のホロヴィッツとは、どちらも同じ19世紀的な
ヴィルトゥオジテの演奏ながら、全く違った行き方として
常に気になる存在となったのである。
そのリヒテルの名盤の一つに、
シューベルトの「ピアノソナタ第21盤変ロ長調 D960」がある。
これは、シューベルトの遺作でもある長い長いソナタで、
「グレート」と呼ばれる彼の第9番交響曲同様、
僕にはとても耐えられない、何をやっているのか
分からないうちに眠ってしまうような曲なのである。
その長い第21番のピアノソナタの名盤と言えば
リヒテルがメロディアに遺した演奏が挙げられることが多く、
僕もその演奏で聴いて知っている曲だったのだ。
が、この曲をホロヴィッツがアメリカデビュー25周年のライヴで
弾いているのを聴いてまた魂消てしまった。
リヒテルに比べると遥かにテンポが速いのだ。
全く違う曲に聞こえると言ってもいい。
この内省的な曲はリヒテルのように弾くのが本来なのだろうが、
テンポを速く取るホロヴィッツは、あっと言う間に4楽章を弾いて
聴く人を飽きさせない。
これもまた楽譜通りかどうかを別にして、
無視できない名演と言っていいだろう。
そしてチャイコフスキーの「ピアノ協奏曲第一番」である。
これも、カラヤン/ヴィーン交響楽団と共演した
1962年録音のグラモフォン盤の評価が高く、
やはり自分もこの演奏で聴いていたのだが、
最初に書いたホロヴィッツの『展覧会の絵』を
CD で買い直した時に、そのカップリングがこの曲だったのだが、
ホロヴィッツが奏でるピアノの響きにも
トスカニーニ指揮の NBC 交響楽団が奏でるオケの音色にも
参ってしまった。
何と言う濃厚な、19世紀的な音。
現代的な演奏が次々に出て来ている中で、
これはいかにも大時代的な、甘ったるい音なのだが、
その甘ったるさこそが僕らの魂の深いところをくすぐるのである。
僕は長い事チャイコフスキーは苦手だったのだが、
もしかして、ホロヴィッツのこの絢爛豪華な演奏こそ
チャイコフスキーのこの曲を有名にしたのではないか、
そんなことを思わせる演奏なのである。
そう、これもまた無視できない演奏なのだ。
ところでホロヴィッツと言えば、例の吉田秀和さんが
『世界のピアニスト』の中でこのように書いておられる。
「しかし、さすがのホロヴィッツも、行きすぎて、いわば対象をのりこえて名人芸の空まわりに終わる演奏をしたことも事実だ。たとえば、彼が自分で編曲し演奏した米国国歌『星条旗の下に』のレコード。あれはショッキングだった。私は唖然としてしまった。十九世紀の悪達者な名人たちならいざ知らず、万事につけて合理的になている二十世紀の巨匠で、名人芸が、これほどグロテスクな域に達した演奏は、類があっても、ごく少ないのではないか。貴重なものの無償な浪費こそ楽しいという人もあるだろうが、これは名人の悪趣味の典型みたいなものだった。」
僕がこの文章を読んだのは学生の頃だったと思うが、
吉田さんがここまで酷評する演奏はどんなものなんだろうと
ずっと不思議に思っていた。
しかし、『展覧会の絵』のような大曲の CD は買っても
『星条旗』のようなものをその興味のためだけに買うことは
到底できることではないので、ずっとそのままになっていた。
と、最近、昔 LP で持っていたホロヴィッツが弾いた
メンデルスゾーンの「無言歌」を聴きたくなって
RCA から出ている小品集を買ったらそこに入っていたのだ、
「星条旗よ永遠なれ」が。
どれどれ、と思って聴き始めたら、暫くして
僕は可笑しくなって笑い出してしまった。
この曲は勿論スーザが書いた吹奏楽の曲なのだが、
ホロヴィッツは10本の指でその吹奏楽の各パートをの音を
弾き分けるのだ。
ピアノからピッコロの音が、トロンボーンが聞こえて来るのだ。
そう、これは一人吹奏楽と言っていい演奏。
『展覧会の絵』で、これでもかこれでもかと
原曲にはない音を追加した人らしく、
一人で吹奏楽の各パートを弾き分けるのだ。
これはもう、音楽的な演奏というより曲芸の範疇に入る。
吉田さんがグロテスクとか悪趣味と言ったのは
きっとこのことだったのだろうと今更のように思うのである。
しかし、ピアノを使ってこんなことができる、
ピアノを使ってこんな音が出せる、
ピアノという楽器の表現力をとことん突き詰めた演奏というのが
これまで述べて来たどの曲にも言えると思う。
だから無視できないのだ、同じピアノを弾く人間にとっては。
それは、決して模範的な演奏ではないかもしれないけれども
音楽というのが表現の芸術である以上、
ここまで追究された表現を、同じ表現者としては無視できない。
それは、好きとか嫌いとかを超えた何かなのだ。
かくして、この1年ばかりホロヴィッツの CD は
たくさん買って聴いた。
好きとか嫌いとかでなく――癖になるのだな、これは。w


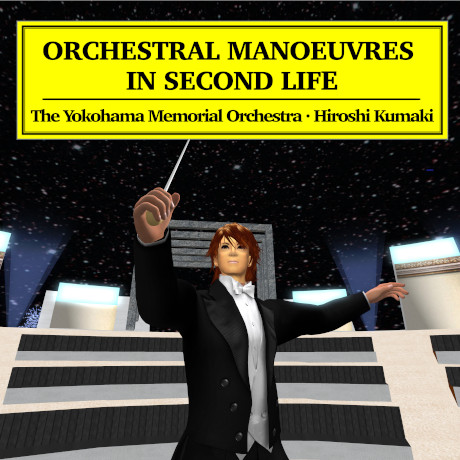


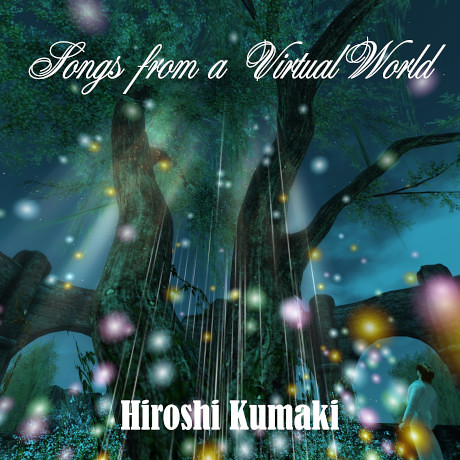

No response to “ホロヴィッツのこと”
Leave a Reply