ここ数か月、取り組んでいることのために
あまり SL にログインしたり、この日記を書くこともなかったですが、
その間も音楽はいろいろと聴いていました。
昨年小澤征爾さんが亡くなって、小澤さんの CD を
改めて聴き直すようになってから気づいたのですが、
既に廃盤になっていて新品では手に入らなくて
ずっと探してはいても諦めていたようなものも
中古屋さんに行くと案外手に入ったりするものです。
それでここ1年ほどは時間があれば中古屋さんを覗いて
何か掘り出し物がないか、物色したりしています。
そんな音源の一つがロシアのピアニスト
ラーザリ・ベルマンが弾いたベートーヴェンの
「ピアノソナタ第23番ヘ短調作品57『熱情』」です。
これは、僕が生まれて初めてそれと意識して聴いた
「熱情ソナタ」で、それだけにいろいろなピアニストによる
名演と呼ばれるディスクが多数ある中で、
自分としては最も「熱情」らしい「熱情」だと
感じて来たものなのでした。
確か、同じベートーヴェンのピアノソナタ第18番との
カップリングで出ていた LP を持っていましたが、
それは親の家にあって、もう何十年も聴いたことがなく、
CD では一度も見かけたことのない演奏なのでした。
それが、やはり中古屋さんで、
Lazar Berman - The Complete CBS Recordings として
6枚組のセットで、しかも驚くような安い値段で
出ているのを見つけて迷わず購入して聴いたのでした。

「熱情ソナタ」を聴くと言ったら、やはりベートーヴェン弾きの
バックハウスとかケンプとか、全集を録音している
グルダとかブレンデルとかで聴くのが間違いないでしょう。
そこへ行くとベルマンは特にベートーヴェン弾きというわけでなく、
実際、この CBS に録れた全集版でもベートーヴェンの曲は
先に挙げた「熱情」と第18番のソナタのスタジオ録音と
1979年、カーネギーホールのライブで弾いた
第8番の「悲愴ソナタ」くらいしかありません。
ベルマンは元々 1963 年にソ連のメロディア・レーベルから出た
リストの『超絶技巧練習曲』で西側に知られるようになった
ピアニストで、19世紀的ヴィルツゥオジテを自負してるだけあって
リストやラフマニノフといったテクニック的に難しい
曲を得意とするピアニストというのが
世間一般の評価ではないでしょうか。
そう、だから僕もベルマンの「熱情ソナタ」のことは
気になりつつも、リストやラフマニノフはあまり得意でない僕は
結果的にベルマンの CD は買わずに来たのですが、
ある時作曲家で評論家の諸井誠さんが
その著『ピアノ名曲名盤100』の中で次のように書いていたのです。
「ベルマンの《超絶技巧練習曲》もショッキングだった。頭がぐらぐらしてくる音なのである。しかし、こうしたショックは、反面で拒絶反応も起しかねない。この盤をあんまり何度も聴くと、私は完全なリスト嫌いになりそうだ。このレコードは吉田秀和さんの新聞時評を読んで関心を持ち、聴いてみたのだが……。」
この文章で久しぶりにベルマンに出逢って、
ほう、あのベルマンが。。。と思いながら、
「頭がぐらぐらしてくる音」とはどんな音か興味を持って
CD を手に入れて聴いたのであった。
確かに、この演奏は凄い。頭がぐらぐらするというか
目が回るというか、とんでもない演奏なのです。
なるほど、これで彼に対するイメージが固まってしまったとしても
それは仕方のないところかもしれません。
そのベルマンが何故ベートーヴェンの「熱情ソナタ」を選んだか?
実は、同じようにベートーヴェン弾きではないにも拘わらず
このソナタを何度か録音している人にホロヴィッツがいます。
そして、そのホロヴィッツが 1959 年に録れた RCA 盤に対して
かの吉田秀和さんは『LP 300選』の「レコード表」の中で、
「胸のすくような名演」と評しておられます。
ホロヴィッツもまたヴィルトゥオジテの人で、
ベートーヴェンのこの曲はそのヴィルトゥオジテを発揮するに
持って来いの曲だったのでしょう。
実際、デュナーミクと言い、アゴーギクと言い、
ホロヴィッツ特有の癖のある演奏でありながら、
最初の出だしからフィナーレまで一気に聴かせる
説得力に満ちた演奏なのです。
これを聴いてしまうと、案外全集盤で定評のある
バックハウスが色褪せて感じられます。
ホロヴィッツについては書きたいことがいろいろありますので
また稿を改めることにしますが、
ベルマンもホロヴィッツと同じ流れのピアニストだと感じます。
彼にとっても「熱情ソナタ」はそのヴィルトゥオジテを
遺憾なく発揮できる曲だったのでしょう。
実際、久しぶりに聴いて思いましたが、
あの「頭がぐらぐらしてくる」リストの『超絶技巧』と同じ何か、
一つ一つの音に込める「熱さ」のようなものが感じられるのです。
そしてそれこそが正に、「熱情」という曲にピッタリのもので、
この通称がベートーヴェン自身が付けたものにないにせよ、
「熱情」というテーマを意識してこの曲を聴く時
このベルマンの演奏ほどピッタリなものはないのではないか、
そのように思える演奏なのです。
その熱い感じがキラキラと輝くような綺麗な音色と
正確なリズムに支えられているのですから奇跡的と言えます。
(ホロヴィッツは時に雑に感じられることもありますからね。w)
生まれて一番最初に聴いた演奏だから先入観があるのだろうと
ケンプやバックハウスやグルダの演奏を聴き直しましたが、
この曲は誰が弾いても面白く聴けるように作曲されていながら、
やはりこの熱さだけはベルマン特有のものだと思いました。
あ、ホロヴィッツもですが、それについてはまたの機会に。。。
尚、ベルマンの名前は今の日本では「ラザール」と
フランス語風に表記されることが多いのですが、
僕が1970年代の終わりに初めてその名前を聞いた時は
「ラーザリ」とロシア語風の発音で呼ばれていました。
なので僕の中ではずっと「ラーザリ」なので
今回もそのロシア語表記で書かせて戴きました。


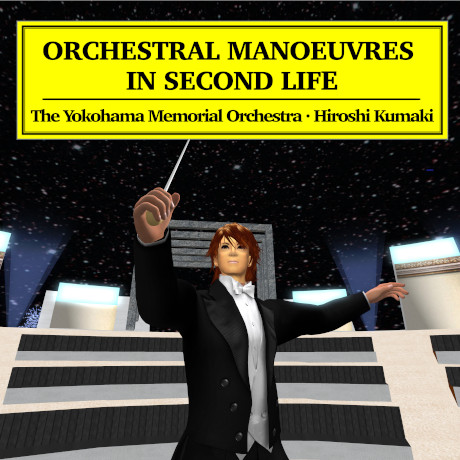


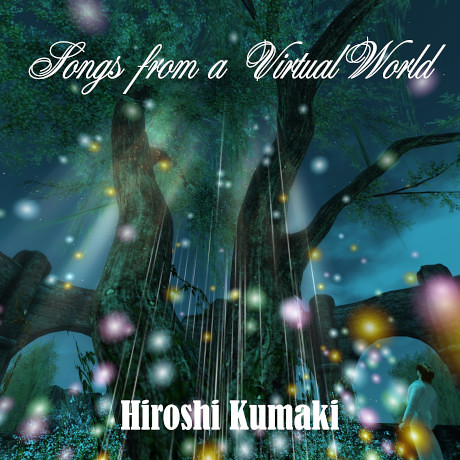

No response to “ラーザリ・ベルマンの「熱情」ソナタ”
Leave a Reply