う〜ん、どこから話そう。
生成文法のことである。
「文法」と言えば皆さんがイメージするのは
高校の時に学んだ「英文法」や、中学校の時の「国文法」であろう。
これらの文法の体系は元はと言えば言語学から来ているが、
その言語学は古代ギリシャのホメロスの叙事詩などを
解読するために生まれたものだと言っていい。
ホメロスの叙事詩を解読するために書かれている文のルールが
一つ一つ検討され、そこで所謂「品詞」のような
単語のカテゴリー分けや活用表などが作られたのだ。
これが後にローマ帝国の時代にラテン語にも応用され、
更にヨーロッパ語の文法体系の規範となっていくのである。
やがて、研究が進むにつれ、サンスクリットなどのインドの言葉と
ヨーロッパ諸語は起源が同じであることが明らかにされる。
インド=ヨーロッパ語族と呼ばれるようになるそれである。
起源が同じであるとわかると話は早い。
古代ゲルマン語のこの単語はプロヴァンス語のこれに当たる、
というようなことがわかると、あと、それぞれの言語のルールが
わかると、ほぼ機械的に置き換えによる翻訳が可能なのである。
そして、日本でもまた、文字というものは中国から入って来た
漢字を使うようになり、中国語と日本語は語順が違うので
返り点を打ったり、中国語にはない「てにをは」を補うことで
中国語を日本語として読むことが可能になったのである。
これもまた、機械的な置き換えによる翻訳と言えるだろう。
これらヨーロッパでも日本でも、何れの場合でも、
表現されている「文」の置き換えができれば、
その内容を理解できるという考えの下に
言語学乃至は国語学は現在に至っていると言っていい。
しかし、日本語には有名な「僕はうなぎだ」という文例がある。
これは勿論、友だちと定食屋に行ってメニューを決める時の発言で、
「僕はうなぎにする、うなぎに決めた」という意味で、
別に特殊でもなんでもない普通の表現である。
が、これを従来の文から文への置換を行うと
英語では "I am an eel." というアヤシイ内容になってしまう。
時枝誠記(ときえだもとき)さんという国語学者がいて、
この方は学位論文で「言語過程説」というのを打ち立てた。
即ち、発話というのは音楽や絵画や小説や詩と同じように
その人の表現の一形態に過ぎないのであって、
音楽や絵画や文学がその背景にその作曲家や画家や作家の
表現したいものというのがあるのと同様、
言語による発話にもその背景に表現したい何かがあるのだ、
従って発話(文)そのものの意味というのは絶対ではない、
といったことを訴えたのだ。
その学位論文が出たのが1925年。
そして、1955年にノーム・チョムスキーという人が
「生成文法」の元になる考え方を示す。
何故、子供は文法を勉強せずに正しい言葉づかいを覚えるのか?
それは、どのような言語であれ、その言語に触れる経験を重ねる中、
ほぼ自動的にその言語のルール、文法を整理構築する能力を
人間は生まれながらにして持っているのだ、という考えであり、
チョムスキーはこの能力を「普遍文法」と名付けた。
この普遍文法について僕なりに理解しているところを
下の図に整理してみた。

最近、AI 翻訳になって何故翻訳の精度が上がったか。
つまり、以前の機械翻訳に「この本は読んだ」と入れると
"This book read." という訳が返って来ていたが、
今はちゃんと"I read this book." と訳してくれる。
これは、AI がそれぞれの言語の膨大なデータベースに基づいて
より精密なルールでこの文の意味はきっとこうだと
普遍文法的な処理をしているからだろうと僕は見ている。
(言い方を変えると、AI の真似をして
たくさんその言葉を経験すれば語学の上達は早いのだ。^^)
この生成文法が前提にしているのも、時枝さんと同じく、
話者の頭の中にあるイメージ、内容である。
これを日本語のルールを通せば「僕はうなぎだ」になるし、
英語のルールを通せば "I'll take an eel bowl." となるのだが、
頭の中のイメージを抜きにして「僕はうなぎだ」を
文のレベルで訳してしまうと "I am an eel." になってしまうのだ。
(こう考えると、例えば日本語を英語に訳す時、
いきなりその文を英語で置き換えようとするのでなく、
話者の頭の中のイメージに一回変換するとよいのだ。)
時枝さんは言語は音楽や絵画、文学と同じ表現としたのだが、
バーンスタインはこの逆に音楽も言語と同じ表現形式としたのだ。
「答えのない質問」の講義が言語学の用語である
音韻論、統語論、意味論で始まるのはある意味必然なのである。


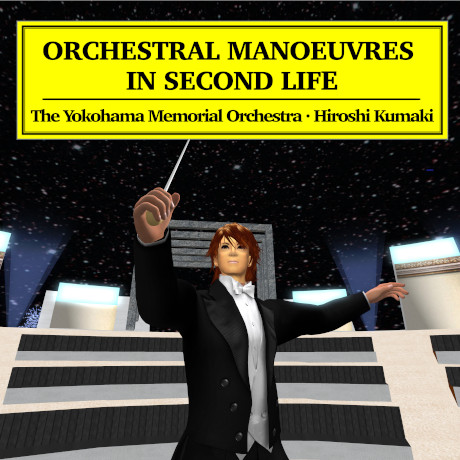




No response to “近況報告〜音楽哲学の試み・その4”
Leave a Reply